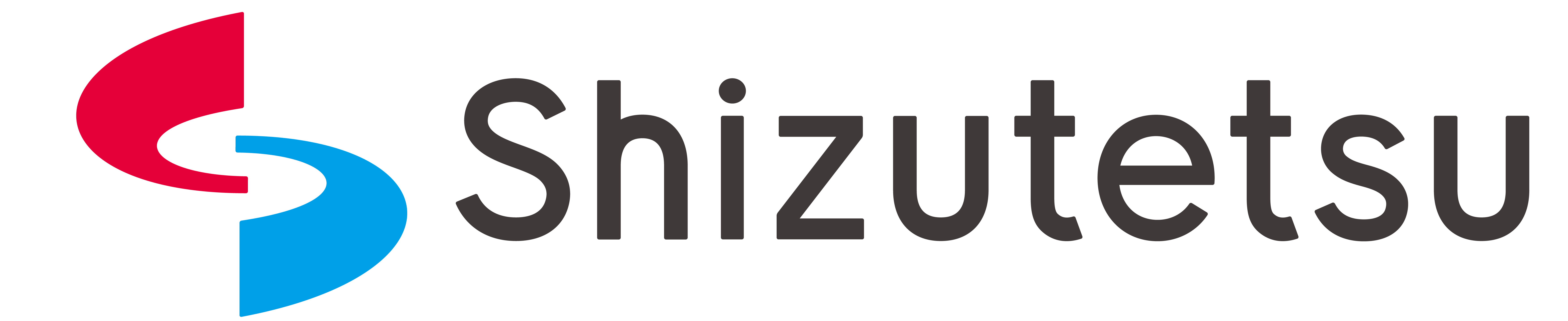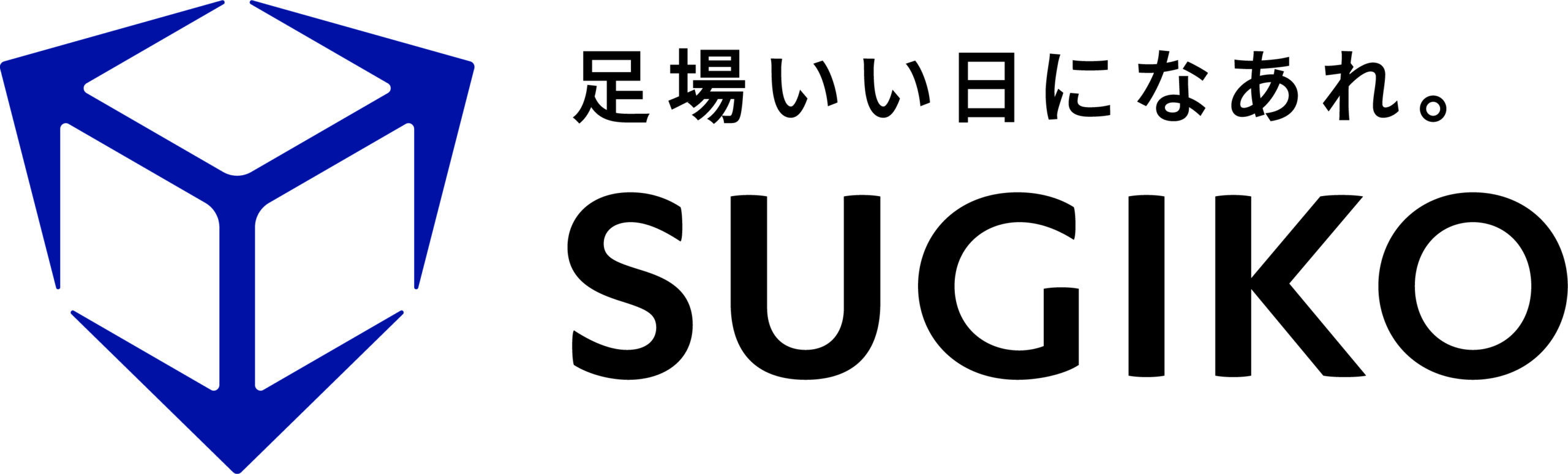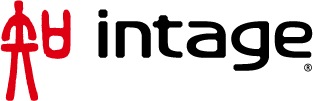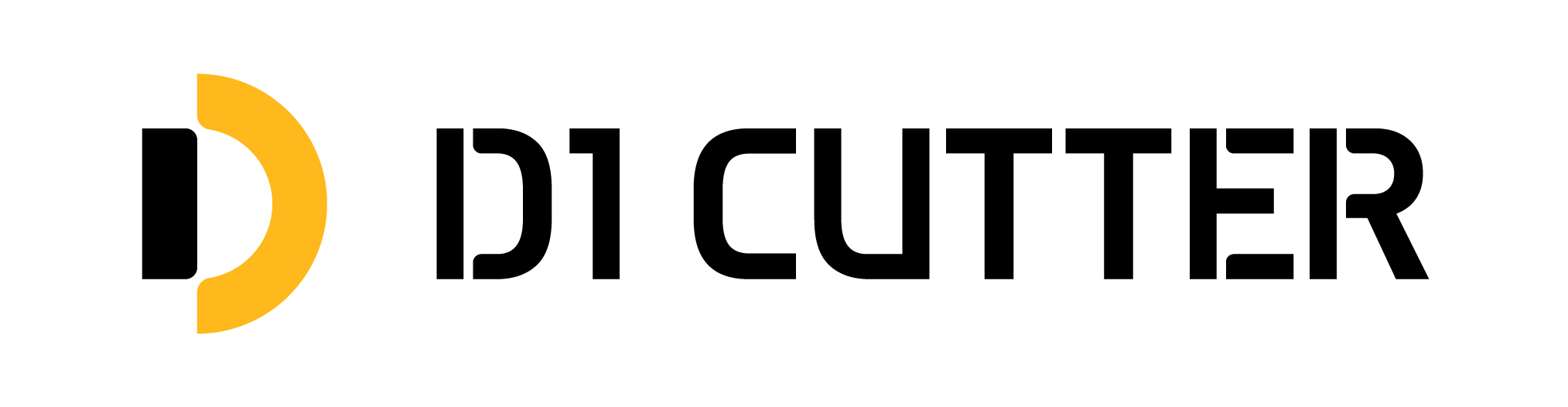静岡県を中心に、鉄道やバス・タクシー、自動車販売や不動産、宿泊や小売など、幅広いサービスを展開する静鉄グループ。静岡鉄道株式会社はグループの中核企業にあたり、1919年の創業から人々の暮らしを支えています。
今回は、静岡鉄道株式会社の採用全般を行っている人事部 人財採用課の課長である住吉さん、係長の神村さん、主任の山田さんに取材し、Bizer team導入の背景や成果についてお伺いしました。
採用業務の複雑化による業務ボリューム増と、ジョブローテーションに伴うナレッジのリセットが課題
――Bizer team導入前の課題を教えてください。
住吉さん:
人財採用課は、静岡鉄道株式会社の採用全般を行っています。私は商業施設の運営や他社留学(人材交流による他社での人事経験)などを経て7年前に着任しました。神村さんは3年前に異動し、中途採用とグローバル人材の採用支援に携わっています。山田さんは昨年まで研修を担当する人財育成課に所属し、今年度から人財採用課に異動になりました。
人財採用課の課題は、主に「業務効率化」と「ナレッジ蓄積」の両立でした。労働人口減少によって採用の難易度が上がっているため、採用業務は複雑化しています。その結果、業務ボリュームは増加傾向にあり、効率的に業務を進める必要がありました。
一方で、目の前の業務に追われがちな日々で、個人的なメモはあっても引き継ぎで使えるような完成度の高いマニュアルがなく、チーム全体でナレッジを蓄積できていないという課題もありました。共通で使っているツールやフォーマットも統一しきれていなかったので、メモ書きの人もいればツールを使っている人もいるなど、管理方法も人によってバラバラでした。弊社はジョブローテーションがあるので、担当者が変わることは珍しくありません。小規模で多忙なチームで担当者が変わった際に、もし後任にしっかりと引き継ぎができないと、溜まったナレッジがゼロになってしまう懸念を抱えています。
神村さん:
業務の抜け漏れも課題でした。メンバー同士が多忙な上に、「お願いします」「分かりました」という口頭やチャットでの依頼なので、お互いに業務内容や進捗を把握できていませんでした。「既読になって安心していたら、作業が進んでいなかった」「どのように作業するのか分からず止まっていた」など、結果的に依頼した業務が漏れてしまうこともありました。
――Bizer team導入の経緯を教えてください。
住吉さん:
チャット中心の運用で起きる抜け漏れや、誰が何を抱えているか見えないといったボトルネックを解消するため、タスクを可視化し履歴として蓄積できる専用のしくみが必要だと感じました。そこで、タスク管理ツールの検討を始めて周囲にもヒアリングをしたところ、Bizer teamの名前が挙がりました。タスク管理だけなら様々なツールがあると思いますが、ジョブローテーションで担当者が頻繁に変わるため、忙しくても時間をかけずに使えるツールが必要だと感じていました。選定の際に大事にしたのは、「タスクを可視化できること」「マニュアルとして機能しブラッシュアップできること」の2つです。Bizer teamは、求めていた2つの要件に加えて、扱いやすいところがすごく良いと思いました。説明書がなくても直感的に使い方が分かるし、必要十分な機能でとてもシンプルなのが気に入りました。
導入にあたっては、パワーポイントで説明資料を作って上司に提案しました。まず、業務ボリュームが増えている現状を伝え、「業務が可視化されておらず、ナレッジが蓄積されていない」というチームの課題を理解していただくところから始めました。「Bizer teamを導入すれば月にこれだけ業務を効率化できる見込みがあり、導入コストを上回るメリットがある」ということも説明し、チームのあり方など課題解決のための他の手段も併せて伝えました。

導入・定着はマネージャーと現場責任者の2名で推進。Bizer teamに触れる機会を増やしたことも浸透の要因
――Bizer teamを定着させるために心がけていたことはありますか。
住吉さん:
導入・推進は誰か一人だけに任せるのではなく、複数の推進者で進めていくということです。今回のチームでは私と神村さんが一緒になって導入・推進を進めました。我々が積極的にBizer teamを使うとともに、「Bizer teamに全部登録して」「これをBizer teamに反映して」という会話を徹底しました。また、途中からは「Bizer teamにタスクを登録すること」を「バイザる」という言いやすい言葉で表現することで、より日常に浸透することを狙いました。Bizer teamに限らず、言葉を統一するのは浸透させるためにとても大切で、日常で発する言葉に混ぜるとメンバーの意識も揃っていくと思います。
また、週に1度の定例会で、メンバーが見直したテンプレートの共有をしています。他にも、2週に1度「帰りの会」という場を設け、チームのバリューとなる推奨行動を見かけたら、Bizer teamに入力してお互いに褒め合っています。こういったタスク管理以外のポジティブな使い方をしてBizer teamに触れる機会を増やしたことも、浸透した要因のひとつだと思います。
神村さん:
住吉さんや私に仕事の依頼をすると、必ず「バイザっといて」と言われるので、メンバーにも依頼前にBizer teamに登録するという行動が浸透していきました。「Bizer teamに入力しないと動いてもらえない」というのが肌感で伝わったことが大きいですね。
とはいえ、最も大きな要因としてはBizer teamに対して、メンバーの心理的障壁が高くなかったことかと思います。同時期に中途採用の管理について他のシステムを導入していたのですが、難解で心理的な障壁が高くなってしまい、周知してもなかなか使ってもらえませんでした。習熟度に差が出てしまうと、慣れている人は頻繁に使うけれど、慣れない人は使うことが辛くなってしまいます。チームのみんなが使いやすいからこそ、Bizer teamは誰も仲間外れにならずに定着が進みました。
採用業務の99%はBizer teamに蓄積。「バイザる」という言葉が日常になるほどチーム内に定着
――Bizer teamの成果を教えてください。
山田さん:
導入・定着が進んだ結果、採用業務の99%はBizer teamに登録されています。Bizer teamに登録するのが習慣化されているし、テンプレートを作って更新するのも浸透しています。先述のように「バイザる」というチーム内用語もあって、何かを依頼すると「バイザっといて~」と言われます。急ぎで判断してほしいものや当日中の依頼の時だけは、チャットツールを使っています。
Bizer teamの使い方として「入社手続き」のタスクを例にすると、「労働条件の明示」「内定承諾」「入社時備品の手配」などのセクションごとにチェックリストを作成しています。内定を出してオファー面談を実施する際には、労働条件通知書も作成する必要がありますが、関連する作業がリスト化されているだけでもありがたいですし、急ぐ必要があるかどうかの判断もできます。引き継ぎの際も、前任者がそばにいなくても、Bizer teamを見ればやるべきことが分かるのは大きいです。実際に私も人財採用課へ着任したばかりの頃、Bizer teamを見れば自分だけで作業を進めることができたので、とても心強かったです。

ただ、経験者がチェックリストを作成すると、業務を理解しているだけに無意識に判断している作業が抜け落ちてしまうこともあります。未経験者でもチェックリストを見れば抜け漏れなく全ての作業ができるように、備忘録も含めてテンプレートをブラッシュアップするようにしています。
神村さん:
Bizer teamに業務内容が可視化されているので、以前と同じ時間で仕事の質を高めることができたことが大きな成果だと感じています。Bizer teamがあれば仕事のやり方を説明する必要がなくなるので、「なぜこの仕事をするのか」という仕事の意味や背景の説明に時間を使うことができます。意味や背景を知ることで、「この順序の方が良いのでは」「この作業は不要かもしれない」など、改善に向けた議論ができます。Bizer teamを導入したことで、業務の抜け漏れが減ってナレッジが蓄積され、業務改善まで踏み込めるようになりました。
住吉さん:
「バイザる」という言葉ができるほどナレッジを蓄積する文化ができたことは大きな成果で、実際に助けられたエピソードがあります。Bizer teamを導入して1カ月ほど経った頃、実施する予定だったインターンシップの日に台風が来ることが分かり、急遽オンラインに切り替えることになりました。幸運なことに、すでにBizer teamにインターンシップのタスクが登録されていたので、それを利用してリアルタイムでオンライン向けの作業をチェックリストに追加し、みんなで分担して準備することにしました。学生さんへの案内やオンライン向けの資料の更新、社員座談会のメンバーへの連絡など様々な業務があったので、Bizer teamに登録されていなかったら徹夜だったかもしれません。ナレッジが蓄積されていたからこそ、突発的なトラブルにもチームで対応できました。
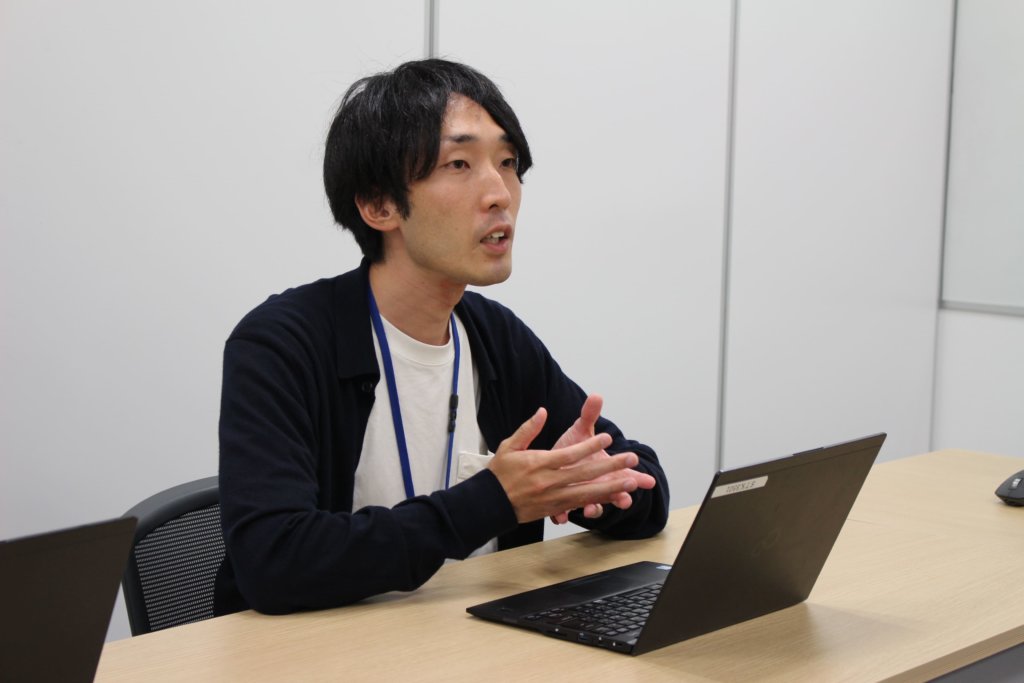
みんなで力を合わせるのが静岡鉄道のカルチャー。お互いにギブし合えるチームへ
――今後、どんなチームにしていきたいですか?
住吉さん:
みんなで作っていくのが街づくり。「みんなで」というのは静岡鉄道のカルチャーでもあります。圧倒的なエースプレイヤーが頑張るのではなく、みんなで作っていく、みんなで良くしていくのがチームの理想像です。
Bizer teamのおかげもあって理想のチームに近づいているので、蓄積したナレッジをみんなでブラッシュアップし、今後はさらにレベルアップしていきたいですね。
神村さん:
自分が人事に来たばかりの頃は、様々な業務が口伝になっていて背景も分からない状況でした。現在は、ナレッジをBizer teamに残して改善するという文化ができているので、継続していきたいと思っています。
Bizer teamはとても便利なツールですが、慣れすぎると未導入の部署とのやり取りに不便を感じてしまいます。密かな野望として、他の部署にもBizer teamが広がらないかなと考えています(笑)
住吉さん:
バックオフィスは全てBizer teamが導入されていても良いし、会社にとっても事業成長に繋がると思っています。Bizer teamの魅力は、「チームみんなで作る」という点に加えて、「自分のためにテンプレートを更新すると、誰かのためにもなる」という点です。自分のための作業が他のメンバーやチームのためになるという、双方がギブする関係につながります。誰かにギブされた経験があれば、他の誰かにギブしようという気持ちになり、ギブし合える優しいチームになると思っています。